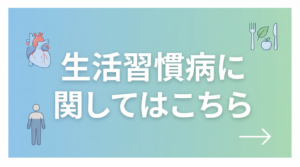糖尿病は防げる!原因から学ぶ、今日からできる生活改善5選
糖尿病予備軍と診断された方へ
「健康診断で糖尿病予備軍と言われてしまった…」「でもどうしていいか分からない」そんな不安を抱えていませんか?「糖尿病」と言われると精神的にショックを受ける方は多くいらっしゃいます。
しかし、糖尿病は自覚症状が出にくい「サイレントキラー」とも呼ばれる病気で、気づかないうちに進行する厄介な疾患です。
日本では成人の約6人に1人が糖尿病またはその予備軍とされ、年々増加傾向にあります。特に40歳以上では4人に1人が該当するといわれるほど身近な病気になってきています。糖尿病予備軍と診断された段階で、心筋梗塞や脳梗塞のリスクが上昇することが分かっています。しかしながら、糖尿病は生活習慣の改善によって十分予防が可能な病気でもあります。糖尿病予備軍と診断された方は今日からできる対策を一緒に考えてみましょう。
「本当は怖い生活習慣病。がんとの関係も!」に関してはこちらをご覧ください。
糖尿病の基礎知識と原因
まず、糖尿病とは血糖値が慢性的に高くなることで全身の血管や神経に負担をかけ、様々な合併症を引き起こす病気です。代表的な合併症には、失明につながる網膜症、慢性腎不全、神経障害による手足のしびれ、さらには動脈硬化が進行することで心臓病や脳卒中の原因にもなります。これらの合併症は血糖が高くなることにより、血管がダメージを受け、発症します。糖尿病にはいくつか種類がありますが、日本人の大半は生活習慣と関係深い2型糖尿病です。
では、なぜ血糖値が高くなってしまうのでしょうか。その背景には遺伝的要因と環境要因(生活習慣)が組み合わさって発症することが分かっています。例えば血の繋がっている方に糖尿病の人がいると、ご本人も糖尿病発症しやすい傾向になりますが、それだけで必ず糖尿病を発症するわけではありません。血糖値に対しては日々の食生活や運動習慣の影響が大きく、摂取カロリー過多や肥満によってインスリンの効き目が悪くなると血糖値が上昇しやすくなります。
加えて運動不足は筋肉による糖の消費を減らし、血糖が利用されにくくなるためこれもまた糖尿病発症のリスク因子となります。また加齢に伴い膵臓の機能が低下し、インスリン分泌量が減少すること、太りやすくなりインスリンが効きにくくなるインスリン抵抗性という状態も高血糖を招きやすくなります。そのほか喫煙や慢性的なストレス、睡眠不足なども複合的に糖尿病の発症に関与すると考えられています。つまり
「遺伝だから仕方ない」と諦める必要はなく、生活全般を見直すことで発症リスクを大きく下げられるのです。
実際の症例紹介:生活習慣改善で数値が改善したケース
ケース:50代男性Aさんの例
定期健診でHbA1c(ヘモグロビンA1c)が6.2%と指摘されたAさんは、「糖尿病予備軍」と診断されました(一般的にHbA1cが6.5%以上で糖尿病が強く疑われ、5.7~6.4%が予備群と分類されます)。自覚症状はなく仕事も忙しかったため初めは実感が湧かなかったそうです。しかし、テレビ番組で糖尿病の特集を見られ、放置すると将来の合併症リスクが高まると知り、「今ならまだ改善できるはず」と生活習慣の見直しを決意されました。
まず夕食後のデザートや間食を控え、毎食野菜から食べ始めるよう心がけました。さらに通勤時に一駅分歩くなど日常に運動を取り入れ、週末には適度なジョギングを開始。睡眠もできるだけ確保し、ストレス発散のために趣味の時間を持つようにしました。その結果、3か月後の再検査ではHbA1cが5.8%まで低下し、体重も数kg減少。数値の改善に伴い「この調子で続ければ糖尿病を防げる」という自信につながったそうです。
Aさんの例のように、
薬の力を借りずに、生活改善によって糖尿病の数値を改善できるケースは少なくありません。大切なのは「まだ大丈夫」と先延ばしにせず、今日からできることに取り組むことです。
今日からできる生活改善5選
1. バランスの良い食事を心がける
食生活の見直しは糖尿病予防の第一歩です。ポイントは「適切なエネルギー量とバランスの良い食事」を規則正しくとることです。例えば以下のような点に注意してみましょう。
- 野菜から先に食べる: 食物繊維の多い野菜や海藻類を最初に食べると血糖値の上昇がゆるやかになると言われており、「ベジタブルファースト」と言われています。毎食たっぷり野菜を摂りましょう(目安は1日小皿5皿分、350グラムです)。
- ゆっくりよく噛んで食べる: 早食いは血糖値の急上昇と食べ過ぎにつながります。よく噛むことで満腹中枢が刺激され、少量でも満腹感を得やすくなり、食べ過ぎ防止になります。
- 高GI食品を控える: GI値とは、グリセミック・インデックス(Glycemic Index)の略で、食後血糖値の上昇度を示す指数のことです。つまりこのGI値が高い食材を食べると血糖値が急上昇し、反対に、GI値が低い食材を食べると血糖値は緩やかに上昇します。GI値(グリセミック・インデックス)の高い食品、例えば白米や菓子類は血糖値を急激に上げます。主食は玄米や全粒粉パンなどGI値の低い穀物を選び、甘い飲料を避け無糖のお茶や水にするなど工夫しましょう。
- 間食・夜食の管理: 糖尿病の方にとって、間食や夜食は血糖コントロールに大きな影響を与えます。空腹を我慢しすぎると低血糖やドカ食いにつながるため、適切な内容と量を選ぶことが重要です。低GI食品や食物繊維の多い食品、ナッツ類やヨーグルトなどがおすすめです。夜食は就寝2時間前までに少量にとどめ、糖質の多い菓子やジュースは避けましょう。
これらを心がけるだけでも血糖コントロールの改善に繋がります。規則正しく1日3食を腹八分目でとり、飲酒は適量に留めることも大切です。最初は難しく感じても、少しずつ習慣化していきましょう。一般的に食事療法の効果が出てくるのに数カ月は必要と言われています。最初に自分に厳しくし過ぎると続かないことが多いので、小さいことから少しずつ取り入れていくことが長く続ける秘訣です。
生活習慣病の食事療法についてはこちらもご覧ください。


2. 適度な運動習慣を持つ
運動は血糖値を下げる強力な味方です。筋肉を動かすと糖がエネルギー源として消費され、インスリンの効きも良くなるため血糖コントロールが改善します。血糖値を下げるということを考えた時に適している運動は有酸素運動と呼ばれるウォーキングや軽いジョギングです。目標は週に150分以上(例えば1日30分程度を週5日)とされています。とはいえ、最初から長時間や激しい運動をする必要はありません。通勤時に少し多めに歩く、エレベーターではなく階段を使うなど日常生活の中で体を動かす工夫から始めましょう。また可能であれば筋力トレーニングも週に2〜3回取り入れてみてください。スクワットや軽いダンベル運動など簡単なもので構いませんが、下半身の筋肉が筋肉量としては大きいので、下半身の筋肉を中心に鍛えることお勧めします。筋肉量が増えると基礎代謝が上がり、血糖値の安定に役立ちます。運動習慣がない方は、まずは無理のない範囲で「継続できる運動」を見つけることが大切です。天気の良い日は散歩をする、家ではテレビを見ながらストレッチをする等、楽しみながら身体を動かすことを日常生活に取り入れていきましょう。
3. 質の良い睡眠を確保する
睡眠不足は意外に思われるかもしれませんが、糖尿病リスクと深い関係があります。寝不足の状態が続くと自律神経やホルモンバランスが乱れ、体内での血糖コントロールがうまくいかなくなります。具体的にはインスリンの働きが低下し、さらに睡眠不足によるストレスで分泌されるコルチゾール(ストレスホルモン)が血糖値を上昇させることにつながります。このため毎日十分な睡眠時間を確保することが血糖の管理においても重要になります。個人差はありますが、目安としては1日7時間前後の睡眠を取り、できるだけ就寝・起床リズムを整えるよう心がけましょう。また良質な睡眠のために、寝る前のスマホ・テレビを控える、リラックスできる入浴やストレッチを取り入れるといった工夫も効果的です。睡眠は体と心の回復時間です。しっかり眠ることで翌日の血糖値が安定しやすくなり、結果的に糖尿病の予防や管理につながります。
4. ストレスを溜めず上手に発散する
現代社会ではストレスも生活習慣病の大きな要因の一つです。ストレスが溜まるとホルモンの影響で血糖値が上がりやすくなり、治療の妨げになることがあります。まずは自分に合ったストレス解消法を見つけましょう。軽い運動や散歩、音楽鑑賞、趣味の時間を持つことは気分転換になり、血糖コントロールにも良い影響を与えます。また、家族や友人との会話も心の安定につながります。我慢せず、こまめに気持ちを発散させることが、健康的な生活を続けるコツです。ストレスを溜め込まないことは糖尿病予防だけでなく心身の健康全般に有益ですので、「頑張りすぎない」「一歩立ち止まって休む」ことも重要です。
5. 定期的に血糖チェックを行う
生活習慣を改善していても、定期的な健康チェックは欠かせません。特に糖尿病予備軍と言われた方は、数値の経過を追うことが重要です。コレステロールや中性脂肪の高値を指摘された方は一緒にチェックすることがおススメです。体調に変化がなくても、半年に一度は採血検査を受けて血糖値やHbA1cを確認しましょう。HbA1c(ヘモグロビンA1c)は過去1~2か月の平均的な血糖コントロールを反映する指標で、糖尿病の診断や予防において非常に有用です。例えば健康診断で境界型と言われた方は、放置せず数か月後に再検査を受けてみるとよいでしょう。最近では自宅で測定できる簡易の血糖測定器もありますが、誤差もあるため医療機関での血液検査がおすすめです。定期チェックによって早期に変化を察知できれば、速やかに対策を強化することで糖尿病への進行を防ぐことができます。生活習慣の改善により数値が得られると、それがまたモチベーションの維持に繋がり、より健康的な生活を続ける原動力にもなっていきます。
当院で受けられる診療と検査
生活習慣の改善に取り組んでも「本当にこれで良いのだろうか…」と不安になることもあるでしょう。そんな時は医療機関のサポートを受けることをおすすめします。神奈川県横浜市神奈川区反町にある本多内科医院では、糖尿病を含む生活習慣病に対してきめ細やかな診療を行っています。総合内科・循環器内科を標榜しており、生活習慣病全般の管理から合併症の予防まで一貫したサポートが可能です。糖尿病に関しては、受診当日に結果が分かる院内検査機器を導入しており、その場でHbA1cの測定が可能です。わずかな採血で数分以内に結果が出ますので、来院したその日に血糖コントロールの評価を行い、結果に基づいた指導を受けることができます。例えば「前回よりHbA1cが上がっているから食事をもう少し見直しましょう」といった具体的なアドバイスを即日受けられるのは、大きな安心につながります。
本多内科医院では、患者様一人ひとりの生活背景に寄り添ったオーダーメイドの生活指導を心がけています。食事内容の相談や運動の取り入れ方なども遠慮なくご相談ください。必要に応じて血圧やコレステロールの管理、最新の糖尿病治療薬の導入(例えば週1回自己注射薬など)についても専門医が適切に判断し、提案いたします。血糖やHbA1cに関しては院内で必要な検査が完結する体制を整えており、忙しい方でも負担少なく継続して通院いただけます。
まとめ:早めの対策で未来を変えましょう
糖尿病は決して他人事ではなく、誰にでも起こり得る身近な病気です。しかし、
「発症を未然に防ぐ」「薬を使わずに血糖の管理を可能にする」ことも十分可能な病気であるとお分かりいただけたかと思います。遺伝的な素因があっても、日々の努力次第で発症を防いだりできるケースは多くあります。大切なのは、糖尿病の予備軍と指摘された時に「今この時期に行動を起こす」ことです。適切な食事や運動、睡眠習慣を身につけることで体は必ず応えてくれますし、何より将来の健康への不安が小さくなります。もし一人での改善に不安がある場合は、遠慮なく医師や専門家に相談してください。専門的な視点から適切なアドバイスを受けることで、効率良く安全に予防に取り組むことができます。早めの対策で未来は大きく変えられます。「糖尿病は防げる!」という前向きな気持ちを持って、今日から少しずつ生活改善を始めてみましょう。
当院でも皆様の健康づくりを全力でサポートいたしますので、気になることがあれば横浜市神奈川区の本多内科医院へご相談ください。

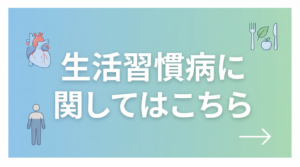
🏥 診療科:内科、循環器内科
🔷 総合内科専門医、循環器内科専門医
📍 Myクリニック本多内科医院(横浜市神奈川区反町4丁目27-1)
この機会に下記の当院公式LINEをご登録ください。
ワクチンの予約に使用できる他、今後多方面での展開を考えております。
監修: Myクリニック本多内科医院 院長 本多洋介