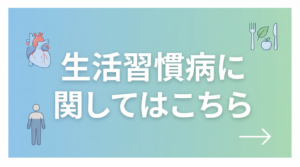見逃しがちな糖尿病の初期症状とは?早期発見のためのポイント
糖尿病は血糖値が慢性的に高い状態が続く病気で、国内外で増加傾向にあります。糖尿病が強く疑われる人の割合は、男性18.1%、女性9.1%と報告されており、年齢が高い層でより割合が高いとされています。初期には自覚症状が軽いため放置されがちですが、放置すると血管や神経を傷つけ、心筋梗塞・脳卒中など重篤な合併症につながる可能性があります
。横浜市神奈川区の本多内科医院では、循環器内科の専門性を活かしつつ、糖尿病の早期発見と治療に力を入れています。この記事では、見逃しやすい糖尿病の初期症状や検査のポイント、当院の取り組みについてご紹介します。
糖尿病の代表的な初期症状
糖尿病の初期には、次のような症状が現れることがあります。
- 喉の渇きと頻尿:体内の血液中の糖分濃度が高くなり、血液の浸透圧が上がると、尿の量が増えることがあります。排尿の量が増えて、体内の水分が減少すると、脱水症状が生じます。それにより、喉の渇き、口の渇きを生じることがあります。。
- 体重減少や倦怠感:細胞内に糖が取り込めないため、エネルギー不足になり、体が脂肪や筋肉を分解して補おうとする結果、体重が減り、身体が疲れやすくなります。
- 視力低下やかすみ目:糖尿病により糖尿病網膜症という状態を引き起こします。糖尿病網膜症は、慢性的な高血糖によって網膜の細い血管が障害されることで発症します。血管の透過性が高まったり閉塞が起きたりすることで、浮腫や虚血が生じ、進行すると異常な新生血管が出現し、視力低下やかすみ目の原因となります。
- 傷や感染の治りが遅い:糖尿病では高血糖の影響で血流が悪化し、白血球の働きも低下するため、感染に対する抵抗力が弱まります。また、神経障害や末梢循環障害により損傷に気づきにくく、傷の治癒が遅れやすくなります。。
- 手足のしびれやピリピリ感:高血糖が長期間続くことで神経が障害される「糖尿病神経障害」によるものです。特に末梢神経が影響を受けやすく、感覚が鈍くなったり異常な感覚が生じたりします。
これらの症状は多くの方が「疲れのせい」や「年齢のせい」と考えがちですが、早期の糖尿病のサインであることも少なくありません。特に、以前より水を飲む量が増えたり、夜間トイレに起きる回数が増えたりした場合は注意が必要です。
見逃しがちなサインと糖尿病予備軍
糖尿病の初期は自覚症状がほとんどない場合もあります。耐糖能異常(糖尿病予備群)と呼ばれる段階では血糖値が正常より高いものの、糖尿病の診断基準には達しておらず、多くの方が無症状です。しかしこの段階で生活習慣を見直すことで、糖尿病の進行を予防できるとされています。
「糖尿病は防げる!原因から学ぶ、今日からできる生活改善5選」はこちらをご覧ください

糖尿病の診断基準と検査の重要性
糖尿病の診断には、空腹時血糖値とHbA1c(ヘモグロビンA1c)という血液検査が用いられます。一般的な基準として、空腹時血糖値が126mg/dL以上、HbA1cが6.5%以上で糖尿病と診断されます。100〜125mg/dLの空腹時血糖やHbA1c 5.7〜6.4%の場合は耐糖能異常(糖尿病予備群)と判断されます。
当院では採血後すぐに血糖とHbA1cを測定できる検査機器を備えています。検査当日に結果をご説明し、生活指導や薬物療法の必要性を判断するため、忙しい方でも負担が少なく受診できます。採血や検査自体は短時間で済み、予約なしでも対応可能です。
早期発見が重要な理由
高血糖状態が続くと、心臓や脳などの血管障害が進行し、重篤な病気に至り、生活の質を大きく損ないます。糖尿病は血管にダメージを与え、まずは眼や腎臓、神経などの微小血管の障害を起こし、失明や腎不全、足潰瘍、感覚障害に至る状態を引き起こします。さらに進行すると、大きい血管にもダメージを与えるようになり、心筋梗塞や脳卒中、足の閉塞性動脈硬化症などのリスクを高めます。糖尿病の人では心血管疾患の死亡率が約2倍に上り、糖尿病患者の死亡原因の約75%が冠動脈疾患とも報告されています。さらに、
こうした
合併症の発症には時間がかかるため、症状がない段階からの血糖管理が極めて重要です。症状に気付いた場合すぐに受診し血糖管理を開始することで、合併症リスクを減らせると強調されています。当院では循環器内科ならではの視点から、動脈硬化に対する検査や治療も同時に行うことができます。
当院における治療とサポート
本多内科医院では総合内科と循環器内科の診療経験を生かし、糖尿病の早期診断・治療に注力しています。具体的には次のような取り組みを行っています。
- 院内での即日検査 前述の通り、当院では血糖値とHbA1cを院内で測定でき、結果を当日にお伝えします。血圧やコレステロールなど心血管リスクも同時に評価し、動脈硬化の程度を総合的に判断します。
- 最新の治療薬の導入 糖尿病領域では新しい薬が年々開発されています。近年注目されているGLP-1受容体作動薬は、インスリン分泌を促し食欲を抑制する作用のある薬で、血糖コントロールと体重減少の両方に効果があります。最近の報告では、これらの薬は血糖値を効果的に下げるだけでなく、体重を減らし、コレステロールを改善すると報告されています。さらに、他の糖尿病薬と比較した研究でも、GLP-1受容体作動薬は心血管イベントや全死亡リスクを減らす効果があると示されています。当院では、患者様の体質や合併症を考慮し、効果と副作用のバランスを見ながら積極的にGLP-1作動薬を取り入れています。
GLP-1作動薬などの薬に関してはこちらをご覧ください。
のエビデンス~-300x300.png)
- 動脈硬化性疾患の管理 糖尿病は心血管疾患のリスク因子であり、血圧や脂質の管理も不可欠です。当院では頸動脈エコーや血圧脈波検査などを用いて動脈硬化の評価を行い、降圧薬や脂質異常症治療薬を組み合わせることにより、全身の血管を守ります。
- 生活習慣へのサポート 食事や運動、睡眠、ストレスなどの生活習慣は糖尿病管理の基礎です。看護師や総合病院の管理栄養士と連携し、患者様のライフスタイルに合わせた具体的なアドバイスを行っています。
実際の症例から学ぶ
50代女性のAさんは、最近「喉が渇いて水分をたくさん摂るようになった」「疲れやすく体重が減った」と感じて当院を受診されました。院内で血糖値を測定すると、空腹時血糖が225mg/dLと高値で、HbA1cは8.9%でした。この時点で糖尿病と診断し、即日薬物療法を開始しました。Aさんは内臓脂肪が多く血圧やLDLコレステロールも高めだったため、SGLT2阻害薬とGLP-1受容体作動薬を順次導入しました。薬物治療と食事・運動療法の併用を続けた結果、2か月後にはHbA1cが6.3%まで改善、体重が3kg減少し、血圧やコレステロールも改善しました。Aさんは「最初に糖尿病と言われた時は怖かったけど、振り返ってみると早めに受診して良かったわ」と喜んでおられます。
まとめと受診のすすめ
糖尿病は初期症状があっても軽微である場合、気のせいと思われやすい場合が多く、気付かれにくい病気ですが、早期に発見して適切に管理することで心臓や脳、腎臓などの重大な合併症を予防できます。喉の渇きや頻尿、視力のかすみ、原因不明の体重減少、疲れやすさ、手足のしびれなどが気になる方は、放置せず医療機関で検査を受けましょう。当院では血糖値やHbA1cは受診日に短時間で測定できます。特にご家族に糖尿病の方がいる場合や、生活習慣に不安がある場合は定期的な検診をおすすめします。
本多内科医院では、一般内科疾患はもちろん循環器内科の視点から、糖尿病と動脈硬化の管理を包括的に行っております。糖尿病領域では最新の治療を取り入れながら患者様の生活に寄り添ったサポートを心がけていますので、どうぞお気軽にご相談ください。

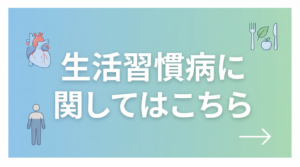
🏥 診療科:内科、循環器内科
🔷 総合内科専門医、循環器内科専門医
📍 Myクリニック本多内科医院(横浜市神奈川区反町4丁目27-1)
この機会に下記の当院公式LINEをご登録ください。
ワクチンの予約に使用できる他、今後多方面での展開を考えております。
監修: Myクリニック本多内科医院 院長 本多洋介



のエビデンス~-300x300.png)