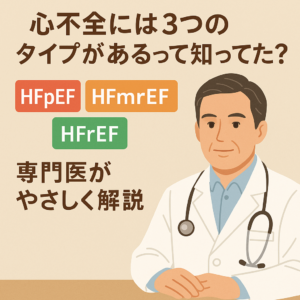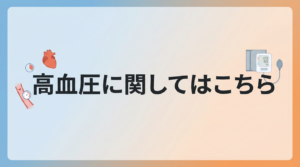高血圧を放置すると“心不全”に?医師が教える原因・予防・治療のポイント
その「様子見」、本当に大丈夫ですか?健診で血圧が高いと言われた、階段で息切れが増えた――そんな小さな変化の裏側で、心臓には静かに、しかし確実に負担がかかっています。高血圧は心筋を厚く・硬くし、拡張しにくい心臓(HFpEF)や収縮力の弱い心臓(HFrEF)へつながることがあります。早めに状況を”見える化”し、生活と薬物療法を適切に組み合わせれば、将来の“急に悪くなる状態(急性増悪)”を減らすことが期待できます。今回は高血圧と心不全という疾患の関係についてまとめていきます。
“心不全には3つのタイプがあるって知ってた?HFpEF、HFmrEF、HFrEFを専門医がやさしく解説”に関してはこちらの記事もご覧ください
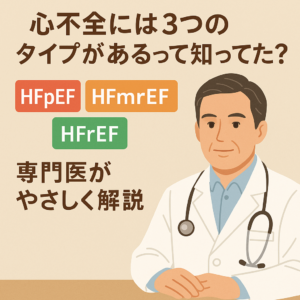
高血圧と心不全:ポイントは“心臓の硬さと広がりにくさ”
高血圧が長く続くと、心臓は重い荷物を持ち続けるのと同じ状態になります。最初は心筋が厚くなって耐えますが、次第に硬くなり拡張が妨げられ(HFpEF)、さらに進むと収縮力の低下(HFrEF)を合併することがあります。心不全の診断や治療方針は
、症状や所見に加え、収縮脳の指標である心エコーでの駆出率(LVEF)や拡張能の指標を総合して決めるのが国際的な基本となっています。
拡張障害を起こしていても初期は無症状であるため、心不全の”ステージB”という状態になります。
“早期発見がカギ!心不全4つのステージと治療の選択肢”の記事はこちらもご覧下さい

30秒で出来るセルフチェック:受診の判断基準
黄信号(当日~数日以内の受診を推奨)
- 前より階段や坂で息切れが増えた
- 夕方になると足のむくみが強い
- 短期間の体重増加(例:数日で約2kg)が続く
赤信号(すぐに医療機関へ受診しましょう)
- 横になると息ができない・起き上がらないと苦しい
- 泡状の赤みがかった痰、急な激しい息切れ
- 冷汗、強い胸痛、意識が遠のく感じ
迷ったら診療時間内に当院へお電話ください。緊急時は119番/#7119をご利用ください。
放置するリスク:悪化のスパイラルを断つ
「そのうち良くなるかも」と様子見をしていると、心機能や心不全はどんどん悪化していきます。収縮力の低下や拡張障害が進み、息切れ・むくみ・体重増の“波”が短い間隔で押し寄せるようになります。心不全の増悪で入退院を繰り返すと、心機能だけではなく、四肢や体幹の筋力・腎機能は落ち、日常生活の質(QOL)も低下しがちです。早い段階での生活介入とガイドラインに沿った薬物療法の開始が、心不全悪化の連鎖を断つ近道です。
当院での診断と検査
- 問診・診察:症状の出方、日内変動、服薬状況、睡眠や食事も丁寧に確認
- 心電図・採血(腎機能・電解質・BNP/NT-proBNP)・胸部X線
- 心エコー:左室拡張能(E/e′、左房径など)とLVEFを確認
- 必要に応じて24時間心電図検査(ホルター心電図)も検討
上記の検査を当院では当日に行います。これらの結果を総合して、心不全の有無・心不全のタイプ(HFpEF/HFmrEF/HFrEF)と高血圧の重症度・合併症をまとめ、これからの生活習慣の改善で必要なこと、薬物療法の導入について説明してきます。
家庭血圧は“平均”で見る:診察が変わるメモ術
朝と就寝前にそれぞれ1〜2回、3日以上測定して平均をみましょう。上腕式の自動血圧計をおすすめします。数値に加えて、外食や濃い味の食事、寝不足、飲み忘れなど、その日の出来事を一言メモすると、診察での解釈が格段に精密になります。一般に、診察室140/90mmHg以上、家庭135/85mmHg以上は高血圧の目安とされます。※持病・年齢によって目標値は変わってきます。
治療の考え方:一人ひとりに最適化した薬物治療
高血圧の薬物療法
ARB/ACE阻害薬、カルシウム拮抗薬、利尿薬、必要によりβ遮断薬などを、家庭血圧のパターンや合併症(糖尿病・腎臓病・睡眠時無呼吸など)を踏まえて最小限の組み合わせから開始します。血圧の推移を見ながら、内服薬の調整を行っていきますが、自己判断での中断や増減は避け、副作用や体調の変化はまずご相談ください。
慢性心不全(特にHFrEF)への薬物療法
HFrEFではARNI/ACE阻害薬/ARB、β遮断薬、MRA、SGLT2阻害薬といった“ファンタスティック4”言われる心不全治療の根幹となる薬物治療を段階的に揃えることが推奨されています。最近されたガイドラインではHFmrEFやHFpEFでもSGLT2阻害薬の有効性が示され、選択肢が広がっています。腎機能・血圧・脈拍を確認しながら、少しずつ安全に用量調整します。
急性増悪を防ぐ
息切れの急激な悪化、横になれない、夜間の咳、急な体重増・むくみ、泡状の痰、強い胸痛や冷汗、意識が遠のく――これらは救急対応の目安です。この”急性増悪”を防ぐことが心不全治療において重要なことの一つです。普段から「悪化サイン」をご家族と共有し、体重と症状の記録を続けておきましょう。
症例でみる:高血圧と心不全のリアルな関係
症例1:50代女性―高血圧を契機に心不全入院。退院後は血圧管理で安定(HFpEFの一例)
受診のきっかけ
健診で高血圧を指摘されていたものの忙しさから受診が後回しになっていました。数か月後、階段での息切れが強くなり、夜間の咳や横になると苦しい感じ(起座呼吸)が出現し、近隣の総合病院に救急入院となりました。
入院時の評価
胸部X線で肺うっ血、血液検査で心不全を示唆する所見を認めました。心エコーでは駆出率(LVEF)は保たれている一方、左室がやや厚く、拡張能の低下がみられ、HFpEFの診断となりました。降圧と利尿で症状は改善し、退院となっています。
当院でのフォロー
退院後、当院にて家庭血圧の管理、減塩(外食時の工夫や減塩醤油の使用)、有酸素運動の指導などを行いました。薬物は降圧薬を中心に治療を行ったところ、数週間で日常の息切れが軽減しました。家庭血圧は安定し、体重・むくみの変動も小さくなりました。再評価の心エコーでも駆出率は保たれたままとなっており、以降、再入院なく外来で安定フォローが続いています。
この症例からの学び
- HFpEFは「LVEFが保たれていても苦しい」という状態です。拡張能や左房の所見、心房細動の有無、症状の出方を総合して判断します。
- 家庭血圧と生活メモが、薬の微調整と再燃予防に直結します。
症例2:60代男性―高血圧を放置し、心機能が低下(高血圧心臓病からHFrEFへ)
受診のきっかけ
若い頃から「血圧は高め」。自覚症状が乏しく、長年受診せずにいました。数年後、歩行で強い息切れ、足のむくみ、数日の体重増加が続き、家族に促されて当院を受診しました。
初診時の評価(当院)
初診時、痰の絡む咳、下腿浮腫を認めましたw部X線で心拡大と肺うっ血を疑い、当日検査(心電図・採血・胸部X線)を実施しました。心エコーでは駆出率低下がみられ、HFrEFと判断しました。背景に長期の未治療高血圧による心筋のリモデリングが示唆されました。
治療と外来計画
症状緩和に必要な範囲で利尿薬を用いながら、ガイドラインに沿いARNI、β遮断薬、MRA、SGLT2阻害薬などを腎機能・血圧・脈拍に留意して段階的に導入しました。家庭血圧・体重・症状の3点セット記録をお願いし、管理栄養士も含めて生活指導を行いました。外来での慎重な投薬調整により、息切れは日常生活で許容範囲に改善しました。体重とむくみの変動も小さくなり、再入院なく経過しています。ただし、低下した心機能が完全に元に戻らないと考えられ、今後も「家庭血圧・体重・症状」を軸に、薬の用量調整と生活の工夫を続けていきます。
この症例からの学び
- “症状が乏しくても高血圧は進む”――放置は心筋のリモデリング(構造の変化)を招き、HFrEFに至ることがあります。多くの場合、リモデリングが進み、心臓の線維化が進むと心機能の改善自体は困難です。
- 早期受診と早期治療介入により、症状と再増悪リスクの低減が期待できます。
初診当日に現在の状態を“見える化”
受付、医師の診察後に当日に心電図・採血・胸部X線などを行います。
心不全が強く疑われる場合、心エコーは当日に行い、初診当日に現在の心臓の状態を”見える化”します。結果に応じて、今後の方針や投薬治療について当日にお話しいたします。
当院の強み
- 予約不要:気になったその日に相談できます
- 循環器内科専門医が対応:高血圧から慢性心不全・急性増悪まで継続サポート
- 当日検査が可能:心電図・採血・胸部X線・心臓超音波検査は当日実施を基本としています
- 訪問診療にも対応:通院が難しい方へ、在宅での薬調整・増悪予防を継続支援します。多職種との連携により”心臓を守る在宅診療”を行います。もちろん、必要時は地域の医療機関と連携し、入院の手配なども行いますので、ご安心ください。
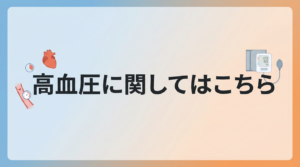
よくある質問(FAQ)
Q1:来院前にできるセルフチェックはありますか?
A:①朝・就寝前の家庭血圧を3日以上記録、②体重の変化、③息切れ・夜間咳・むくみ、④飲み忘れや副作用、⑤濃い味が好き・外食の有無をメモ。これらの情報があると、診断に近づき、生活指導も行いやすくなります。
Q2:血圧が診察室だと高く、家だと普通です。どうすればよいですか?
A:「白衣高血圧」の可能性があります。家庭血圧を重視して評価します。血圧計に不安がある方は、ご家庭の血圧計をご持参いただき、診察室で比較することもあります。
Q3:どの薬から始まりますか?副作用が心配です。
A:合併症・年齢・家庭血圧のパターンで選びます。薬を飲み始めてから何か気になる症状は我慢せず共有してください。自己判断での中断は増悪の元になります。
Q4:「心不全」と言われました。良くなりますか?
A:生活改善とガイドラインで推奨される薬物療法(HFrEFでは4薬クラス、HFmrEF/HFpEFでもSGLT2阻害薬など)を丁寧に続けることで、症状や入院リスクの低減が報告されています。合併症や血圧の数字、心臓の状態によっても目標は異なってくるため、患者さん個々に合わせて治療が必要になります。
Q5:どんな症状なら救急に行くべき?
A:息切れの急激悪化、横になれない、泡状の痰、急な体重増・むくみ、強い胸痛・冷汗・意識の混濁は救急受診の目安です。迷ったら診療時間内にお電話をください。緊急時は119番/#7119へ。
受診のご案内
息切れ・むくみ・体重増加・家庭血圧の高値が気になる方は、ご相談ください。当院は予約無しで対応しています。循環器内科専門医が、当日検査を含めて現状を”見える化”し、現時点で必要なこと・これからのことをお話しします。年齢、足腰が不自由などの理由により通院が難しい方には訪問診療も対応します。
横浜市の心不全診療に関しては横浜市神奈川区の内科・循環器内科クリニックである本多内科医院にご相談ください。
🏥 診療科:内科、循環器内科
🔷 総合内科専門医、循環器内科専門医
📍 Myクリニック本多内科医院(横浜市神奈川区反町4丁目27-1)
この機会に下記の当院公式LINEをご登録ください。ワクチンの予約に使用できる他、今後多方面での展開を考えております。
監修: Myクリニック本多内科医院 院長 本多洋介